エンジニアキャリアの変遷(草稿編)

下書きとして、エンジニアのキャリアをまとめてみました。
取り留めのない時系列メモ
2024年10月

大学2年生の夏休みが明けた頃でした。それまでずっとエンジニアリングはchatGPTに頼っていましたが、初めてインターンに本気でいきたいと思うようになり、大学の先輩にdiscordで質問をしました。 その際教えてもらった本の「APIを作りながら進むGo中級者への道」という本を見ながら基本文法を学びつつ、APIの作成について学びました。 その後は個人で求人サイトのためのAPIを作成しました。この時はプログラミングの面白さに気づき、授業中も授業そっちのけでプロジェクトを進めていました。マネタイズなんかしてしまったりしてなんかも考えていました😅 https://techbookfest.org/product/jXDAEU1dR53kbZkgtDm9zx?productVariantID=dvjtgpjw8VDTXNqKaanTVi
できるようになったこと
- GoでのAPI開発
2024年12月
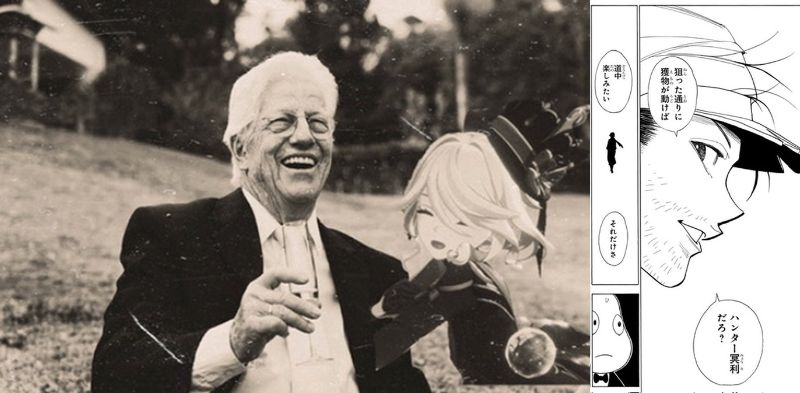
上記のプロジェクトが完成し、いくつかの企業のインターンに申し込みました。申し込んだのは、
- ハウテレビジョン(時給が3500円と高額だったから)
- 任天堂(ブランドがあると思ったから)
- Finatext Holdings(先輩からおすすめされたから)
上記の3社でした。結果はFinatextさんのみ受かり他は全て最終面接で落ちました。 ただ、これまで一次面接が通過したことがなかったので進歩を感じていました。
2025年1月
Finatextさんでバックエンドエンジニアとしてインターンに参加させていただくことになりました。 給料は並より少し低いぐらいでしたが、超フレックスなことと労働力としてではなく、人材として経験の足りない僕を育てようとしてくれる姿勢がとてもありがたかったです。 こちらは5ヶ月ほど続けさせていただきました。主に社内ツール向けのAPIの作成をしていました。
2025年4月
これぐらいの時期からいわゆるメガベンチャーというような企業へのインターンに応募し始めました。 結果はどれも惨敗でした。特に人事面接でよく落ちました。 いくつか面接を受けましたが、結果的に一つも受かりませんでした。インターンとしてではなくアルバイトとして応募したpixivさんで決済基盤の業務をすることになりました。
2025年6月(現在)

pixivでのアルバイトが始まりました。Scala3を使うので、初めはそのために学習をずっとしていました。Hands-on Scala Programmingを使っていました。英語なので苦労しました。どうしてもわからないところは翻訳ツールを使用していました。
またサマーインターンの募集が始まりました。今のところその通過率は0%です。原因としては
- システムデザインの経験不足
- 学歴不足
- コーディング試験の対策不足
などが挙げられます。エンジニアとしてのキャリアは早くも絶たれたのではと考えています。 ここで今までなんとなく考えていた海外の大学院に進むキャリアが現実味を帯び始めます。なぜなら、日本の市場規模だけでは食いっぱぐれるのではという観念が僕を遅い、英語を話せるようにして応募できる求人の数を増やすのがいいと考えたからです。 そして、TOEFLの対策を始めました。とにかく、単語+LR+SWをセットで毎日やる生活が始まりました。「試験とは参考書に書いてある知識をいかに抜けもれなく現地に持っていくか」という考えのもと、単語はもちろん、音声・文法・表現などその日取り組んだすべての範囲でわからないことが一つも無くなるようにしていました。週末はその復習をするようにしていました。 この時期から毎日やることを定めました
- 英語の勉強(3時間ほど)
- アルゴリズムプログラミング(1.5時間ほど)
- OSSのドキュメントを作成する(2時間ほど)
- 大学の授業の復習をする(1時間ほど) ほぼ毎日やっていたこと
- 技術書を1章読む(1.5時間ほど) 英語の勉強は主に留学のためのTOEFLの勉強でした。ただ、モチベーション管理などの面から日常会話などの表現も時々学んでいました。
アルゴリズムは普段はLeetcode、週末はAtCoderのコンテストに出るようにしていました。
OSSのドキュメント作成とはコードを読んで、思考を整理していく作業のことです。声に出したり、コードを動かしてみたり、ゴールは自然言語によりそのプロジェクトが何をやっているのかを華麗に説明できるようになることでした。OSSのコードは日々増大していくので、1ヶ月を目安にレポジトリを切り替えるようにしていました。その際issueでできそうなものがあればPRを投げるようにして実装力も鍛えていました。
大学の授業の復習はテスト勉強の時間を削減しつついい点数を取るためにしていました。留学を意識し出した影響でなるべく高いGPAを取る必要がありました。それまでは直前に詰め込んでなんとかしていましたが、殆ど満点しか許されないという制約のもとではこれぐらいの対策をする必要がありました。課題の出し忘れが減りました。
技術書はなるべく低レイヤのものと研究関連の機械学習の本を読んでいました。ハンズオンのものもあればそうでない難しい技術の解説のようなものも読んでいました。書籍やweb上の記事など内容は様々でした。読む際は、固有名詞などをメモしていました。そして、その単語を見ただけで内容が再現できるように読んでいました。(もちろん、暗記率はひどいものでしたが)。根本的なコンピュータや理論の理解が目的でした。